2019年5月7日
「政治ってクリエイティブな仕事なんです」 超党派での制度改革に挑戦した議員秘書が語る、新しい政治のかたち
料亭政治、利益誘導…。政治家に対するマイナスイメージがついた言葉を探せば、たくさん存在する。いろいろなタイプの議員が出てきているとはいえ、「国民の税金を使って生活し、椅子にふんぞり返って陳情を聞いている」イメージはまだ残っているようだ。
そんな中、「政治って、本当はとてもクリエイティブでやりがいのある仕事なんです」と力を込めるのは、国会議員秘書を15年間務めてきた加藤ちほ。昨年12月、栃木で政治活動を始めた。
加藤は大学生のころ、クラスメイトの誘いで衆院議員の選挙ボランティアに参加。その信条に感銘を受け、民間企業や司法書士事務所を経て、国会議員秘書となった。彼女のターニングポイントは、日常生活に医療機器を必要とする「医療的ケア児」の支援に超党派組織で取り組んだ経験だ。
社会問題を解決するには、「まずは中高年男性が多い今の国会議員構成を、社会の実態と同じになるように、女性や様々な“少数派”が入るように変えること。それから、政治家と行政だけでなく、社会起業家や当事者の人たちの声を制度設計に盛り込むこと」。政治の側が変わらないといけない、と強調する。加藤がいま政治家を目指す理由、実現したい社会像を聞いた。
議員秘書歴15年。国政の荒波をこえてきた
――自己紹介を兼ねて、加藤さんのこれまでの活動について、教えてください。
加藤ちほです。北海道函館市出身で、早稲田大学に進学してからはずっと東京で生活してきました。これまで15年ほど、荒井さとし衆院議員の下で国会議員秘書をしていました。
選挙を何度も戦い、当落ともに経験しました。議員立法にもたくさんかかわりました。特に東日本大震災による福島第一原発事故の収束対策と立法作業では、携帯電話を握りしめて寝ていたくらい、不眠不休で働きましたね。

それぞれの仕事で達成したこと、学んだこともあれば、反省、教訓もたくさんあります。永田町の良いところも悪いところも見てきたわたしだから、他の分野から立憲民主党に入ってきてくれる人たちと協力して、実現できることがきっとあるはず。そう確信して、栃木に飛び込む決心をしました。
宇都宮に引っ越してきて4カ月経ったところです。土地勘もついてきて、毎日のように県内を走り回ってます。

「ありがとう」の電話で気づいた、ほんとうの政治の役割
――政治家を目指すきっかけになったという、「永田町子ども未来会議」について、教えてください。
「医療的ケア児」ってご存じですか?人口呼吸器や経管栄養など、医療機器を日常的につけないと生きられない子どもたちのことです。いまの障がい児支援は、昭和40年代につくられた「大島分類」という障がい判定に基づいています。
当時の医療技術では生きられなかった子は分類に入っていないので、重度の「障がい」と認定されず、必要な支援が受けられなかった。いまも十分とは言えず、親御さんに睡眠を削っての在宅ケアという大きな負担がのしかかっています。

――医療の進歩に法律が追い付いていないんですね。
そうです。この問題を解決するために、お子さんが当事者である自民党の野田聖子議員と、荒井議員が中心となって始めたのが「永田町子ども未来会議」です。
与野党議員に加えて専門家、支援をしているNPO、当事者の子どもたちや親御さんといった関係者が集まって、課題を整理し、制度をどう改善したらいいか話し合う、画期的な取り組みでした。わたしは事務局長として、課題整理や会議運営、省庁との折衝など全体統括を担いました。

――秘書ではなく、政治家としてこの問題に取り組もうと思ったのはなぜでしょう?
2016年には障害者総合支援法改正で、「医療的ケア児」の定義を初めて法律に盛り込んで、自治体が支援する努力義務が課されました。会議の成果のひとつです。その時、親御さんの一人が泣きながら「本当にありがとう」と電話をくれたんです。
秘書の仕事を一生懸命やっていても、それまで「ありがとう」って言われたことはほとんどなかった。だから本当にうれしくて、こちらも涙が出そうでした。政治の外の人とつながって制度を作り上げられる。政治って本当にクリエイティブで、とてもやりがいがある仕事だと気づいたんです。
これまでのように「荒井さとし議員」の名の下ではなく、次世代のために社会をつないでいく仕事に、自分自身が責任をもって取り組みたい。勇気を出して一歩踏み出そうと決心しました。
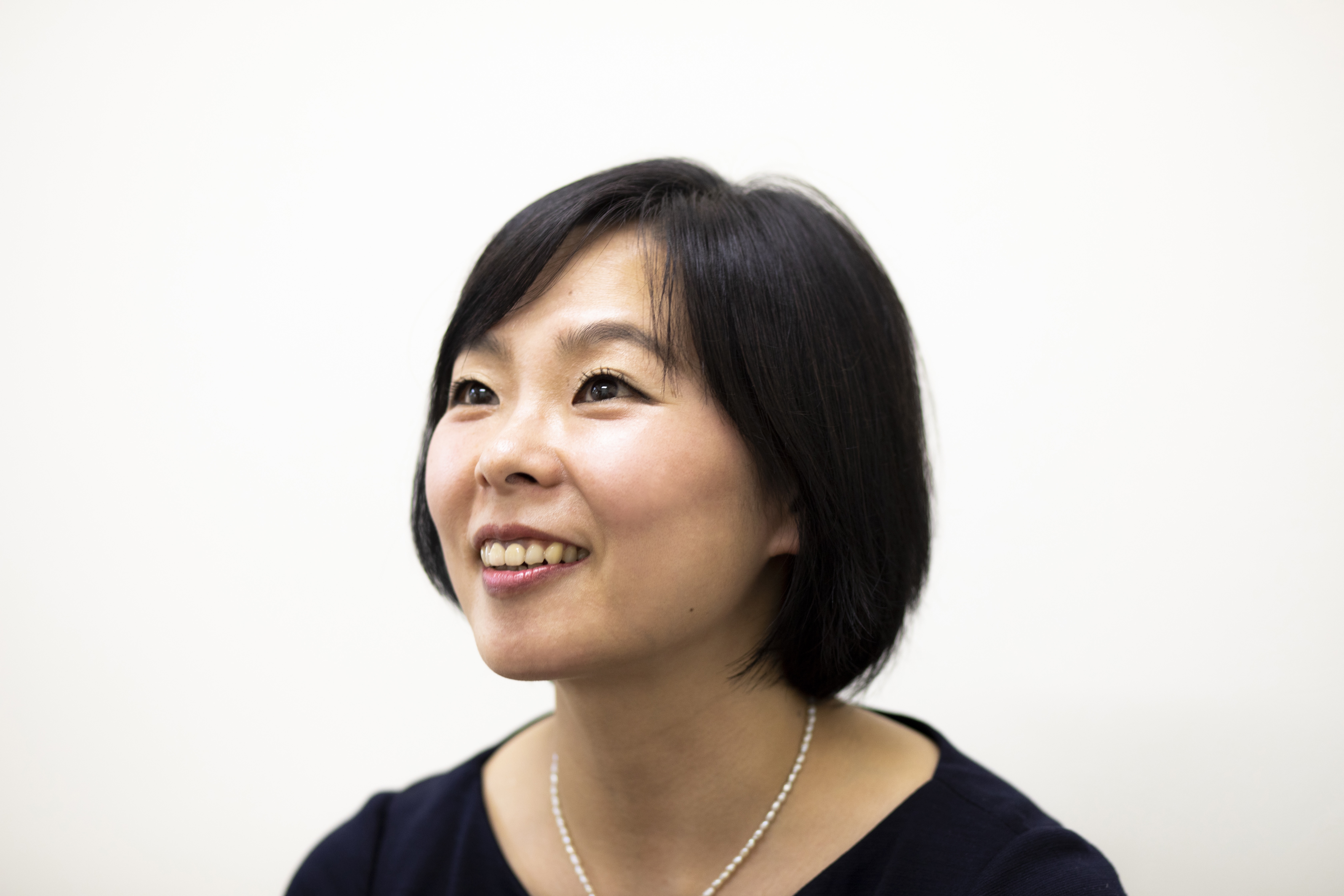
政治が外の世界とつながれば、先端課題も解決していける
――加藤さんのこれまでの国会議員秘書経験は、今後にどう生かせそうですか?
「永田町子ども会議」では、専門家、支援をしているNPO、当事者、政党を超えた議員といった多様な関係者が集まって、課題を整理し、スピード感をもって行政を動かすというモデルをつくることができました。このモデルはほかの社会課題にも応用できるはず。新しい政治のかたちを、広げていきたいです。
関係団体から陳情を受けて、力のある与党の政治家が予算を配分して省庁を動かすやり方は、経済成長期には有効だったかもしれません。ただ、社会の変化のスピードが速い今の時代、従来の政治や行政だけでの解決には限界もあると感じます。

病床の母に後押しされた上京
――加藤さんは早稲田大学の政治経済学部出身です。政治に関心を持って、進学されたんですか?
いえ、物ごころついたころは「料亭政治」という言葉がニュースでよく流れていて、政治家なんてろくなことをしてない人たちだ、というイメージを、大学生のころまで持っていましたね。それにわたし、なかなか自分がやりたいことが分からなくて、若いころはずいぶんふわっとしていたんです(笑)

――どんな子ども時代を過ごされたんですか?
典型的なサラリーマン、専業主婦家庭でした。幼いころは父や弟とキャンプするのが大好きで真っ黒に日焼けしてましたが、小学校に上がるとおとなしくて、本を読んでばかり。
実家の方針でテレビのバラエティー番組を見ていなかったので、友だちとあまり話が合わなくて寂しかったのかも。放課後はよく市立図書館に通ったので、偉人伝の棚を読破しちゃったくらいでした。中学時代も特に熱中したことはなかったかな。
でも、「世の中の役にたつ仕事がしたい」っていう気持ちは、ずっと持っていたように思います。なぜか小学生のころから、大学は必ず東京に出る、と決めていたし(笑) それで、当時先進的な進学指導を取り入れていた女子高を、自分で選んで受験したんです。

――その意思の強さを持ち続けられるのはなぜでしょう?
高校卒業間近に、母が寝たきりになるほどの病気にかかったことがあって。周囲は「弟2人もいるのに、長女が母の世話もせずに東京に出るなんてけしからん」という雰囲気だったんですが、母は毅然として「好きな人生を歩みなさい」って、送り出してくれた。
あの時送り出してくれた母には感謝しかない。どんな境遇の子どもたちもチャレンジできる社会であるために、前に進みたいと思っています。

原点は、「政治家」イメージがひっくり返った選挙ボランティア
――政治にかかわるようになった「原点」はどこだったんでしょう?
大学生のころ、選挙ボランティアに関わった経験です。同じ語学クラスに偶然、荒井議員の息子がいて、選挙を手伝わない?と誘われて。
北海道の選対事務所では、学生が雑魚寝状態。思い思いにボランティアをしてました。自由闊達な雰囲気がすごく心地よかった。荒井さんは街頭演説やあいさつ回りを終えて夜8時ころに戻ってきて、毎晩、40~50人の学生相手にゼミをしてくれたんです。

――どんな内容だったんですか?
国家予算がどんなふうに作られているのか。北海道の課題を解決するには、根幹の国の制度を変えねばと国政に挑戦を決めた話、外交官としての経験談などを惜しみなく披露してくれました。
「政治とは弱きものに光をあてるもの」という考え方も印象的でしたね。困っている人が必要とする法案、制度を作るために、自分は目立たなくても、私心を捨てて身を粉にして働く政治家は存在する。希望を感じました。
そんな熱い思いを持って、学生ボランティアに身体ごとぶつかってきてくれるからこそ、人望がある。「本気で社会を良くしようとしてる政治家は、実行力もあるんだ!」って、それまでのイメージがひっくり返りました。当時の仲間は、社会のいろんな分野の第一線で活躍し、交流が続いています。

「上質なダークスーツの同質集団」による意思決定は限界。いまの政治はひずみが生じた結果
――立憲民主党は議員の男女同数「パリテ」を目指しています。これについてはどう考えていますか?
社会には多様な人がいる一方で、政治の世界は男性だらけ。今もそれが当たり前のまま来ています。わたしも、陳情に来た方たちを迎えようと事務所の扉を開けたら、「男の秘書さんは?」と言われて、悲しくなったことがありました。
同じような価値観、属性の男性ばかりの国会や組織を、わたしは勝手に「上質なダークスーツの同質集団」と呼んでいるのですが(笑)、この集団の意思決定では、社会の変化に応じた制度は作れない。
女性や若い世代、LGBTといったいろいろなバックグラウンド、視点を持つ「ふつう」の人が国会に一定数いれば、先日成立した幼児教育無償化法案のような、現場のニーズを無視したような法案は出てこないはず。今の政治はひずみが生じていると思います。

――具体的に、どんなことに取り組めるでしょうか?
立憲民主党が掲げる「ボトムアップの政治」は、「ふつう」の人たちの声を聞くだけじゃなくて、地域の政治家として活躍してもらおう、という姿勢ですよね。わたしも政治にチャレンジしたい多くの女性、マイノリティを応援する仕組みをつくりたい。
栃木に来てからも政治の現場では女性が本当に少なくて、最初は「どこに行けば女性がいるのか…?!」と思ったほどでした。女性の進出をはばむハラスメントがあれば、できる範囲で声をあげよう、と伝えたい。わたしも栃木に来てから一度、ひどいセクハラを受けました。悩みましたが、県連に相談したところ対策を講じてくれて、それ以降は嫌な思いはしていません。勇気を出して声をあげて、良かったと思います。

観光×農業×再エネで、世界に発信できる先進的な栃木モデルを
――栃木県の可能性について、どう考えていますか?
栃木県は農業、商工業、観光業のバランスがとれた安定した産業構造で、県民所得は全国4位と豊かです。首都圏に近く、人が集まりやすい地方、という特徴もあります。栃木が持つ資源をいかせば、世界に発信できるような、先進的な地域社会モデルが出来るんじゃないか、と期待が膨らんでいます。
県内には那須塩原や日光、鬼怒川など魅力的な温泉地、観光地がたくさんあります。ただ、それぞれのスポットを効率的に移動できる交通手段やパッケージがないので、外国人観光客は県内に宿泊してくれない。各所をつなぐインフラ、仕組みづくりができれば、国内、インバウンドともに観光をもっと伸ばせると思います。

――加藤さんが秘書時代に力を入れていた自然エネルギーについてはどうですか?
原子力発電に依存しないエネルギー政策は、福島原発事故以降の大きな課題です。安定性の高い水力発電のポテンシャルと蓄電池技術のイノベーションを進める政策を組み合わせて系統電線の強化支援をしっかりすれば、県内需要だけでなく東京に電力を送ることもできる。栃木の山間部は高低差が大きく豊富な水量があるので、水力発電に向いているんです。
先日は那須野が原で、小水力発電に先駆的に取り組んでいる女性にお会いしてきました。原発に依存しない社会モデルをつくれる土壌があるんだ、と心強かった。制度間の使い勝手のネックを解消して、エネルギーの地産地消をともに進めていきたいですね。

――栃木県は農業も盛んです。
そう、栃木県の2017年農業産出額は全国9位と上位につけているんです。5年前の大雪では、大平町や栃木市でブドウのビニールハウスが壊れるなどの被害が出た結果、設備投資に躊躇して、ブドウづくりをやめてしまった高齢の農家も多かったそうです。今後も同じように、後継者不足で離農が進む懸念は全国共通です。
一方で、家族経営でも給料制を導入している県内のブドウ農家では、大卒のお孫さん2人が後を継ぐのが決まった、という話を聞きました。一定の安定した収入があれば、若者が地域を出てしまう流れに歯止めをかけられる。
県内の農家さんからは、農家戸別補償制度も含む立憲民主党の農山漁村の未来ビジョンを歓迎する声を聞かせていただくことが多いです。家族経営でも給料が出せるほどの利益を確保できる仕組みの構築を含め、小規模農業でどう地域を活性化できるか、もっと関係者の皆さんの話を聞いていきたいです。

地域で生活できる安定収入のために、「小商い」立ち上げ支援を
――全国的に、地方では人口流出が深刻です。
栃木でも特に山間部では人口減少は喫緊の課題です。小中学校の統合は1回にとどまらず2次、3次もあると聞きます。地方では、医師やその家族が子どもの教育の質を懸念するため、医師の確保がとても難しい。医師の間では「利根川越えたら都落ち」なんて言葉もあるようです。結果、地域で高度な医療が受けられないので、子育て世代や高齢者が流出してしまう、悪循環が起きています。
――栃木ではどのように解決していけそうでしょうか?
分野にかかわらず、地域で安定した収入を得て子育てができるように雇用をつくる。小さいビジネスを山ほど立ち上げることかなと思います。どの地方でも、大規模な工場の誘致を目指すような従来のやり方では、地方創生はうまくいかないことは明らかです。価格競争力の高い海外にも太刀打ちできません。地域の特徴を生かした個性的なビジネスを、金融面や人材育成面で政治がしっかり支える必要があると思います。
そのためにはたとえば、財務会計や新規事業立ち上げの経験がある50代以降の人がセカンドキャリアとして、地域の「小商い」立ち上げを支援することが有効です。そういった活躍の場を広げられるよう、いつでも教育機関に戻って学べる「リカレント教育」の整備も必要だと考えています。

だれもが自立できる機会、居場所のある社会に
――今後国会議員として、どんな社会を実現していきたいですか?
どんな境遇に生まれても教育を受ける機会が保障され、活躍できる、居場所がある社会をつくりたいです。月並みな言葉かもしれないけど、義務教育さえも受けにくい子どもが日本にはまだいることを考えると、本気でこのことは実現しないといけないと思うんです。
医療的ケア児の中には、学校で学びたいのに、介助する親の付き添いが暗黙の条件になっていて、満足に通学できない子がいます。「わたしが悪い子だから学校に行けないの?」という訴えを聞いた時には、政治家だとか秘書だとか関係なくひとりの大人として、この子たちに応えないといけない、と胸がじたばたしました。

――「社会の中に居場所があり活躍できるチャンスがある」というのは、障がい児支援だけでなく、他の分野でも目指さねばならない課題ですね。
そうですね。わたしが「永田町子ども未来会議」の経験を通じて考え続けているのは、「障がい」とか「マイノリティ(少数派)」って何だろう?ということ。言葉を発することができない医療的ケア児の子は、たとえば口元を小さく上げて「うれしい」感情を伝えたり、コミュニケーションをとっていました。どこからどこまで「障がい」かって、とてもあいまいなのに、制度や常識で「健常」とされる側が勝手に線引きをした結果に過ぎないんです。
障がいだけじゃなく、人はいつでもだれでも、何かのきっかけでマイノリティになりうる。多様性を大事にする社会は、いわゆる「多数派」の人にとってもより暮らしやすく、持続可能な社会のはずです。

加藤ちほ CHIHO KATO
1975年、北海道函館市生まれ。1994年 私立函館白百合学園高等学校卒業、1998年早稲田大学政治経済学部経済学科卒業。在学中に阪神・淡路大震災と、第41回衆議院議員選挙へのボランティアを経験。大卒後、民間企業などを経て2003年から衆議院議員秘書、2009年より政策担当秘書。
2011年の福島第一原発事故後に発足した政府の「原発事故収束対策プロジェクトチーム」では事務局統括役を経験。原子力損害賠償支援機構法や、新増設を認めない40年廃炉ルール・バックフィットを導入した原子炉等規制法及び関連法の一括改正、除染の根拠法となる放射性物質汚染対処特措法、議員立法による子ども被災者支援法、原子力規制委員会及び原子力規制庁設置法、憲政史上初の国会事故調査委員会設置法などの成立に関わる。
生まれながらに人工呼吸器や経管栄養などの医療機器を必要とする「医療的ケア児」支援の法的枠組みをつくる超党派の組織「永田町子ども未来会議」では、2015年から事務局長を務めた。趣味はバレエ、ヨガ、座禅。






















